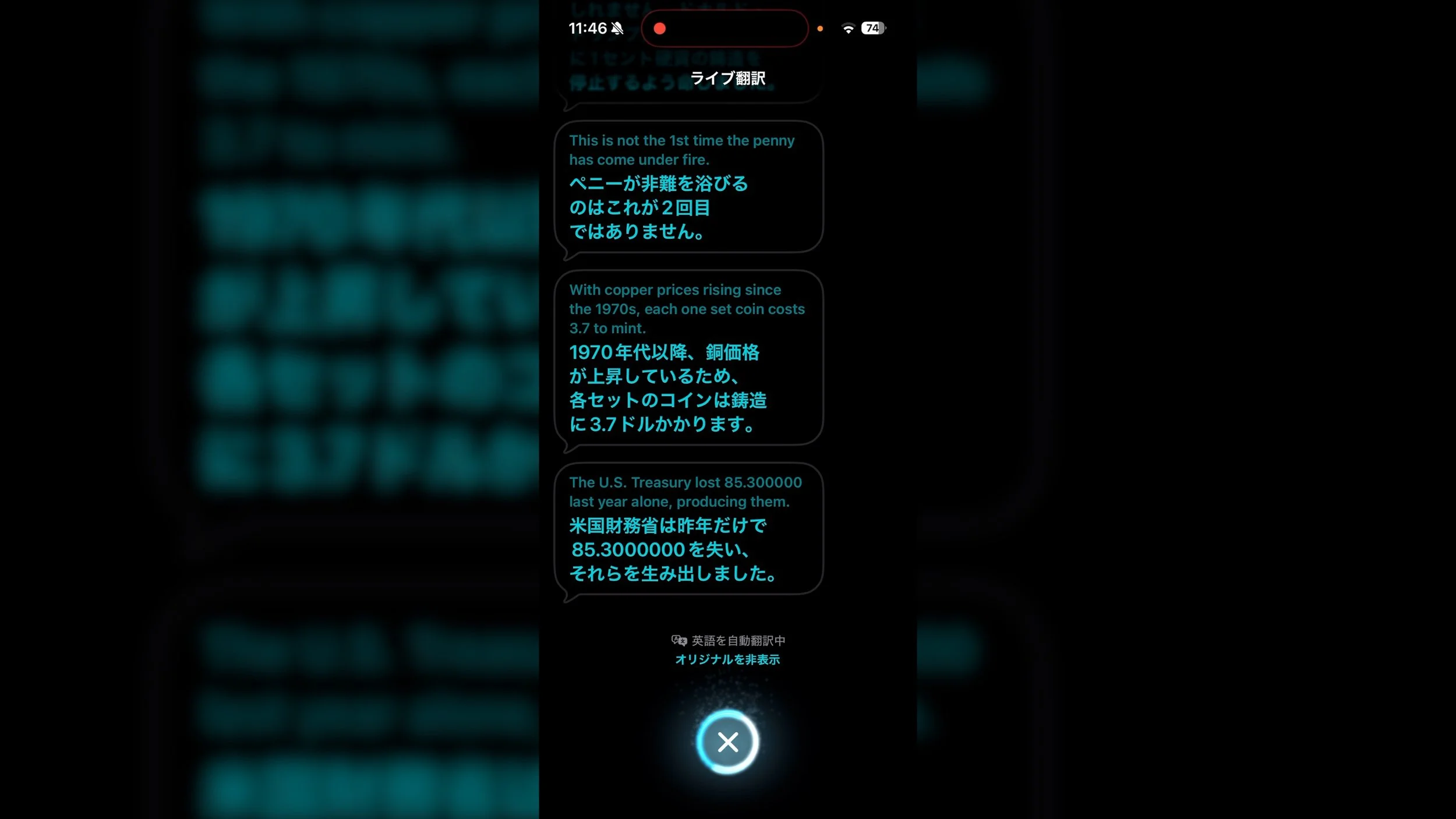iOS 26.1 で日本語対応した自動翻訳機能の正しい使い方
本記事の3行要約
iOS 26.1の自動通訳機能は、正確性を優先しているため発話から訳出までの遅れがあり、会話のテンポにずれを生じやすい。
正確性は概ね許容範囲だが、主語の省略など日本語特有の構造が原因で誤訳も見られる。
ツールとしては会話より展示会やスピーチなど部分理解目的の利用に適し、言語差やツール使用の認識共有が重要とされる。
Apple Intelligence の機能が使えるようになった iOS が、26.1 にアップデートされました。これにより、iPhone に元々搭載されている翻訳アプリで、AirPods と連携して自動通訳機能を利用できるようになりました。相手が英語で話していてもイヤホンからは日本語が聞こえてくる、といったもので、非常に注目を集めています。
そこで、現役の翻訳家・通訳者として、この Apple Intelligence 搭載による英日通訳および日英通訳がどのくらいの精度であるか、また実際にどのようなシーンで使えるか、使う場合の注意点は何かといったことについて、以下の通りまとめます。以下の情報は2025年11月4日時点のパフォーマンスに基づいています。使用した iPhone は 15 Pro です。
音声の遅れについて
同時通訳とは言え、当然ながら通訳をするためには『相手の発話を聞いて、これを必要な言語に変換する』ことが必要ですので、音を聞いてから変換するまでには時間が掛かります。ちなみにプロの通訳者の場合、意味の塊であるチャンクを把握したり先読みしたりして通訳をし、想定と違う流れになったり文法的な違いのために修正が必要な場合には適宜軌道修正をすることもあります。
iOS 26.1 の自動通訳機能について、個人的にはこの音声の遅れが気になりました。恐らくは正確性を優先しているためか、『意味の塊』を大きく取る傾向にあり、そのため『文を言い終わる』まで通訳が始まらないので、実際の会話のテンポからずれていく印象です。
人間の通訳者であっても、逐次通訳などの形態では必ずしも『同時的』な通訳が行われない場合もあります。しかしこのときには会話をしたい二者の間に通訳者が目に見えて存在しているので、通訳者が言葉を変換していることが二者の目からも明らかです。そのため、会話のリズムに対する期待も、通常の二者間でのそれとは異なることになります。
一方 iOS 26.1 のような自動通訳機能だと、見た目では通訳されていることが分かりにくくなります。そのため、より『第三者が入っていない二者での会話』という見え方が強くなり、双方が期待する会話のテンポやリズムは二者間での通常の会話に期待するものに近くなることが想定されます。このとき、iOS 26.1 の通訳に感じられる音声の遅れは、本来期待される円滑なコミュニケーションに悪影響を及ぼす場面があるかもしれません。
正確性について
通訳の正確性について確認したところ、小さなミスがいくつか散見されました。ツールであること、同時通訳を目指す速度でのパフォーマンスであることを鑑みれば許容範囲ではあると思うのですが、正確性が重視される場面や言葉の機微が意味を持つような場面では頼りなく感じます。
また、やはり日本語から英語に通訳するときには、日本語の文の要素を省略して話せるという特徴が通訳の上で障害になっている印象です。主語を取り違えたり、意味の区切りを間違えたりなど、少し不安が残ります。
どのように使うべきか?
上記のように、iOS 26.1 の自動通訳機能は万全とは言い難いところがあります。しかし、急場を凌ぐためのツールとしては使える場面もありそうです。
例えば、会話に用いるにはリズムが気になるという点については、展示会や博覧会といった場面、あるいは一方的なスピーチなどの場面で、ひとまず部分的にでも、あるいは何となくの全体像を理解したいという場合には有効に使えると思います。これは自分が使うケースでもそうですし、充分な準備をすれば、そういったイベントの参加者に Airpods と iPhone を配るなどして説明を多言語化するといったことも可能でしょう。
実際に使用する上での注意としては、言語間で『言わなくても良いこと』に差があることを考慮する必要があるでしょう。これは自分が聞く場合にはもちろん、こちらが喋って相手が iOS 26.1 で自動通訳を使用している場面で特に重要になります。
例えば日本語を話して相手に英語を聞いてもらうような場合、省略の多い文ではなく、主語や目的語などに言及することで、相手にとって聞きやすい英語に変換されることが期待されます。また、英語から日本語の場合、brother と英語で言及された場合には『兄』か『弟』かを区別しなくて良い一方、日本語にするときには必ずどちらかに定めなければいけないので、何かの説明の上では注意が必要です。兄と弟の組み合わせでない『きょうだい』(兄妹、姉弟など)もこれに関連したポイントであると言えます。こうしたことは枚挙に暇がありません。
また、“通訳ツール”との使い分けも考慮するべきでしょう。前述のように、iOS 26.1 の自動通訳機能は、使用していることがほぼ分からないため、却って見た目のコミュニケーションと実際に行われていることに乖離があります。そこで、『今、ここではお互いに相手が分からない言葉を話しているのであり、ツールによってそれを解決している』というコンセンサスを得る目的で、敢えて分かりやすくツールを使うのも良いのではないか、と個人としては考えます。
こうした通訳ツールが今後どのくらいまで進化できるかは想像が難しいところです。ただ重要になるのは、言語変換の精度はもちろんのこと、通訳者が用いている技術をAIが学習できるか(見切り発車で通訳して途中で軌道修正するなどができるか)といったことになりそうです。
もちろん、通訳者の存在が意味を持つ場面も少なくないことから、こうしたツールによってすべての通訳者がいきなり代替されることは、ベストプラクティス的には考えにくいところです。それでももちろん、これも市場の需要によるところですので、翻訳者も通訳者も、自分のサービスがどのような付加価値を持つか、積極的にアピールする必要がありそうです。