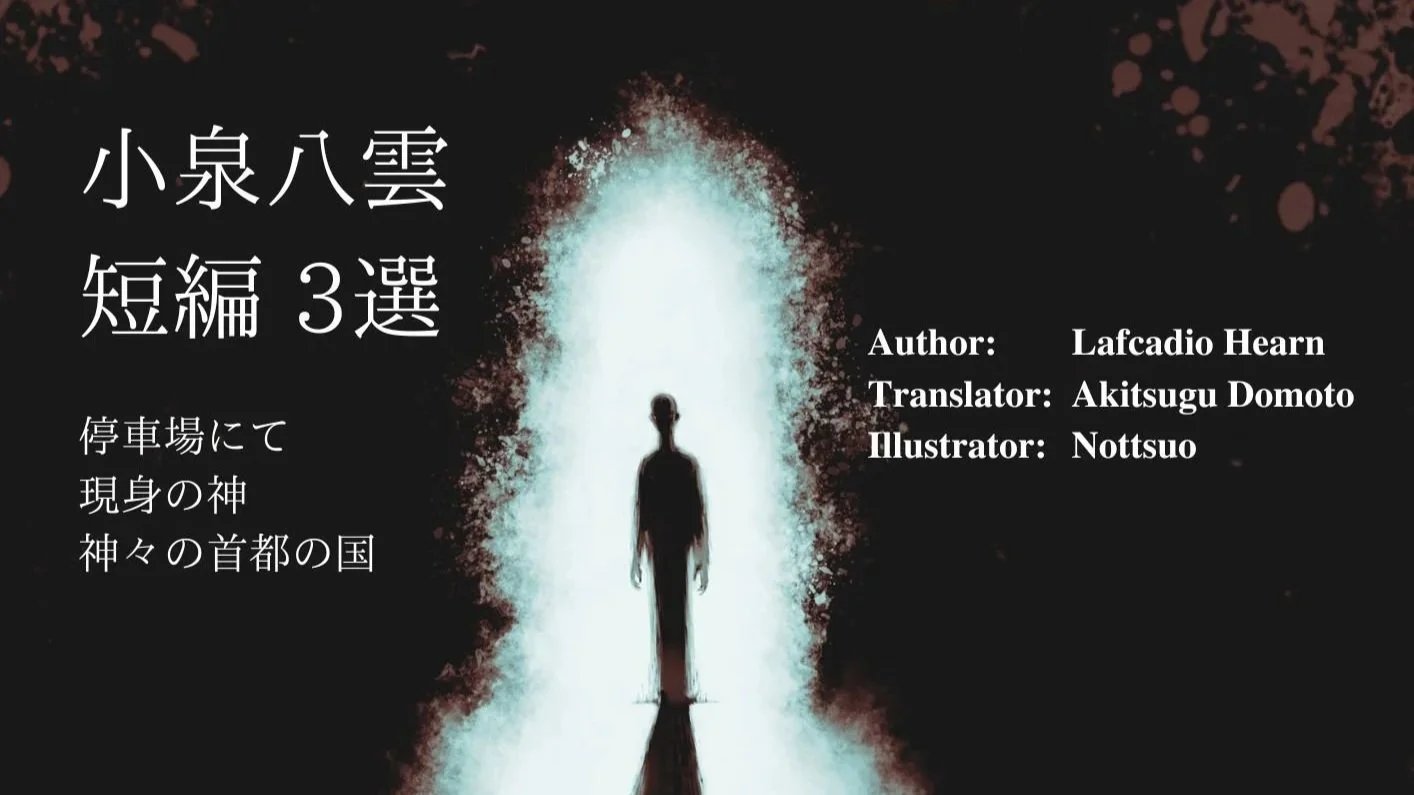方言を取り入れた翻訳に挑戦した理由
方言に対する翻訳の暴力性
以前に別の記事で、ある海外のゲーム(Still Wakes The Deep)が方言を取り入れた翻訳をしたことが話題になっていることを取り上げました。この記事の中では、翻訳のバリエーションとしての価値がある一方、ゲーム体験が損なわれる可能性を鑑みて、方言を翻訳に取り入れることにはリスクもあったことについて触れています。また、ゲームの原文である『スコットランド訛り』を『九州弁』に置き換えて良いのか、という問題もあると指摘しました。
このことは件のゲームだけに当てはまるわけではありません。例えば南部訛りやイギリス訛りなどがある英語の原文で示されているとき、どのように訳出するべきかは難しい問題です。南部訛りやイギリス訛りはあくまで『英語の訛り』であって、それを『日本語の訛り』に置き換えて良いのかという判断があるからです。南部訛りはあくまでアメリカの南部訛りであり、それを具体的な日本の地名に置き換えることは、地理的にまったく異なる場所の言葉使いに置き換えていることになります。
また、方言に置き換えることで、当然、多くのユーザーやオーディエンスにとっては読み難い翻訳になることも懸念されます。翻訳は通常、原文のメッセージをより多くの人に届けるために行われるものであり、方言に置き換えることでその母数を減らすことはこれに反することが多いでしょう。
このような事情から、原文が方言であっても、翻訳においてはスタンダードな翻訳に置き換えられることがよくあります。こうして、『翻訳されたもの』は翻訳先の言語におけるスタンダードな表現(いわゆる“標準語”)に丸められてしまい、原文の機微は失われがちです。これは、方言に対する翻訳の暴力性であり、また同時に、言語の多様性にとっては有害な面であるとも言えるでしょう(とは言え、翻訳すること自体で新たな表現が生まれることもあり、また翻訳調と呼ばれる文体も確立され得ることから、翻訳行為自体が言語の多様性にとっての悪というわけではありません)。
方言と翻訳の付き合い方
では、原文に方言が含まれている場合、そしてこれを何とか訳出したい場合には、どのように翻訳することが可能でしょうか。
ひとつには、特定の方言と対応させず、架空の方言を作り出して翻訳する方法があります。僕自身は、これに近いことをラブクラフト短編集4の『冷気』などで行っています。原文の eye dialect(スペルなどを崩して方言であることを示す表現)となっている部分を、日本語でも崩した表現で対応させている形です。特定の方言と対応させなければ、例えば『南部訛りは関西弁とは違う』のような指摘とは無縁になります。
ただしこれは、あくまで『方言を翻訳する』という点に対するアプローチであり、『翻訳において方言を用いている』わけではありません。果たして、『翻訳で方言を用いる』ことは不可能なのでしょうか。
例えば、ターゲットが非常に狭い場合、ローカライズの一環として『原文が標準語に近くても訳出の際に方言を用いる』という手法が可能である場合もあります。方言を用いることで、それを読みやすいと感じるユーザーは減ってしまいますが、元からターゲットが狭く設定されているのであれば問題はありません。
恐らく、『翻訳と方言』の関わりとして最も大きくあるのはこのふたつでしょう。もちろん、『ある方言を別の方言に置き換える』ことが即ち悪というわけではありません。それはクリエイティブでアートな翻訳ですし、その点で価値があります。しかし、方言の翻訳に当たったとき、常に選べる道ではないことも確かです。
しかしここに、もうひとつ、『方言を翻訳で使う』ことが正当化されるケースがあります。『日本について英語で書かれた文を翻訳する』ケースです。
小泉八雲の作品と地域性
小泉八雲の作品は、いずれも日本について英語で書かれています。つまり、これを翻訳するとき(より正確には舞台となっている場所の人の発言の翻訳時)には、その舞台となっている場所の方言を用いることに妥当性が生まれます。英語では標準語に近い書き方がされていますが、時代背景や地域的特色から登場人物が喋ったときには実際には方言であった可能性が高く、そうした登場人物の台詞であれば、その現地の方言を用いて翻訳することができるのです。例えば熊本を舞台にしたエッセイでは、登場人物が熊本弁で喋っていてもおかしくありません。
この点に注目し、今回、小泉八雲の短編から、熊本県、和歌山県、島根県(出雲)を舞台としたエッセイを抜き出し、登場人物の台詞をそれぞれの地域の方言に寄せて翻訳することを試みました。方言の調査は独自に行ったほか、その地域の出身の方に “ネイティブチェック” してもらったりもしています。
つまり今回の小泉八雲の翻訳は、『翻訳における方言の利用可能性』について考えるための実験的な翻訳でもあるということになります。
アートとしての翻訳の価値
僕は常々、翻訳にもアートとしての価値があるはずだと考えています。また、AI技術の発展によって翻訳の精度が高まってきたこと、それを翻訳業務の中で用いること(MTPEなどのアプローチ)が一般化しつつあることを踏まえると、これに代替されない翻訳の在り方として、そうしたアート的な翻訳の価値は(場所をわきまえて)アピールするべきであるとも考えています。
こうした考えのもと、僕は自分の好みや興味関心に合わせて、折を見て独自に翻訳をしたものを公開しています。こうした翻訳には“クライアント”が存在しないので、 自由に翻訳できる格好です(クライアントに依頼を受けた翻訳はクライアントの納得や要望が第一優先になるので、自分の都合や好みだけで翻訳するわけにはいきません)。
かくして、今回の小泉八雲の翻訳は、そうしたバリエーションとしての翻訳、あるいは翻訳の可能性について考えることの一環となっています。とは言え、読者の視点ではあまり難しく考えずに『面白いエッセイ』くらいで読んでもらえれば嬉しいとも思います。もしも読者がカジュアルに読んでみて面白いと感じるなら、それを試みが上手く作品の中に溶け込んでいると見ることもできるからです。
それでも本ブログは翻訳家としてのブログであり、また読者も翻訳や英語といった言語そのものに興味がある方も少なくないと思うので、普段はあまり『自分はこういうつもりだった』という説明をすることはないのですが、久々にテキストとして考えをまとめるに至りました。小泉八雲の短編、ぜひお手にとっていただければ幸いです。